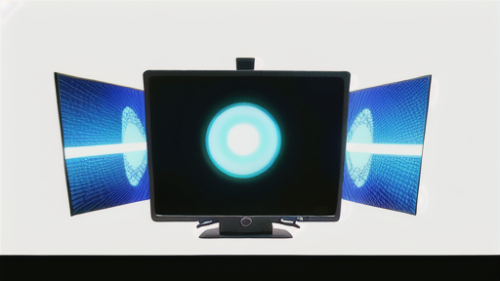規格
規格 動画の基礎:水平同期信号の役割
画面に映像を映すには、電子銃から放たれた電子線が、蛍光物質を塗った画面を左から右へ、上から下へと順番に照らし、光らせる必要があります。この一列の光を走査線と呼び、走査線が何本も集まって画面全体の映像を作っています。では、この走査線はどのようにして正しい位置に描かれるのでしょうか?水平同期信号がその役目を担っています。水平同期信号とは、画面の走査線をどこから描き始めるかを示す信号です。この信号は、映像信号の中に短い電気信号(パルス信号)として含まれています。テレビや画面装置は、このパルス信号を捉えることで、「ここから新しい走査線を始める」という合図を受け取ります。もし水平同期信号がなければどうなるでしょうか?電子銃は走査線を描き始める位置が分からず、画面全体が斜めにずれたり、波打つように歪んで表示されてしまいます。水平同期信号が正確に送受信されることで、走査線の開始位置が一定に保たれ、歪みのない鮮明な映像を見ることができるのです。水平同期信号は、映像信号に欠かせない要素の一つです。高画質で安定した映像を楽しむためには、この水平同期信号が重要な役割を果たしていることを覚えておきましょう。まるで楽譜の音符のように、水平同期信号は画面上の映像を正しく奏でるための目には見えない指揮者と言えるでしょう。