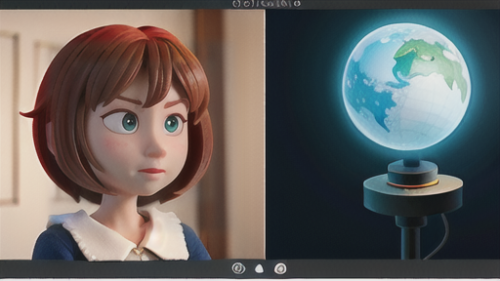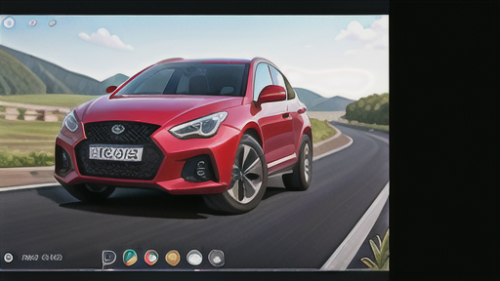画質
画質 映像の乱れ、オーバーシュートとは?
動画を制作する上で、鮮明で美しい映像は、見る人にとってとても大切です。しかし、動画の信号が乱れることで、思いがけない映像の劣化につながることがあります。その乱れの理由の一つに「行き過ぎ」があります。行き過ぎとは、動画信号を波の形で表した時に、本来は平らであるべきところが、針のように飛び出てしまう現象です。具体的には、四角い波の形(矩形波)の立ち上がり部分、つまり信号が低い状態から高い状態に変わるときに、本来の高さよりも高い値を示す、短い針のような波形ができてしまいます。この飛び出た部分が「行き過ぎ」と呼ばれ、映像の質を悪くしてしまうことがあります。例えば、画面に白いものが映った時に、その白い縁の部分がさらに白く強調されて見えたり、本来はなめらかに変化するはずの色の濃淡が、不自然な段差になってしまうことがあります。行き過ぎは、信号が急激に変化しようとする際に、その変化に追いつけずに起こる現象です。行き過ぎを抑えるためには、動画機器の設定を見直したり、信号を安定させるための機材を使うなどの対策が必要です。また、動画編集ソフトを使って、行き過ぎによる映像の乱れを修正することも可能です。行き過ぎ以外にも、映像の乱れには様々な原因があります。ノイズや信号の減衰なども、映像の質を劣化させる要因となります。これらの問題に対処することで、より高品質な動画を制作することができます。