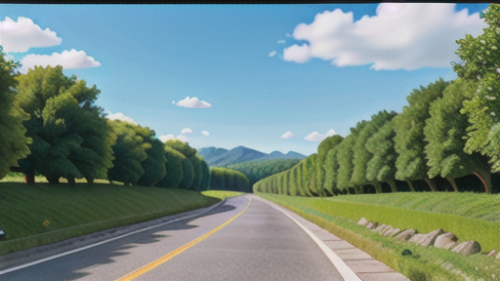規格
規格 ダウンコンバートとは?高画質動画を様々な機器で楽しむ
動画を扱う上で『ダウンコンバート』は欠かせない技術です。 簡単に言うと、高画質の動画を低画質に変換する作業のことを指します。普段あまり意識することはないかもしれませんが、実は様々な場面で利用されています。例えば、皆さんが所有している高性能な携帯電話で撮影した動画を、少し古い型の携帯電話に送信したいとします。最新の機種で撮影した動画は非常に高画質なので、そのままでは古い機種では再生できない、もしくは再生できてもカクカクしたり、容量が大きすぎて送信できなかったりといった問題が発生する可能性があります。このような場合にダウンコンバートが必要になります。動画の画質を落とすことで、古い機種でも再生できるように変換するのです。他にも、テレビ放送もダウンコンバートの一例です。地上デジタル放送は高画質ですが、すべての家庭が対応したテレビを持っているわけではありません。そのため、放送局は高画質の映像をアナログ放送に対応した画質に変換して放送しています。このように、様々な機器で同じ映像を楽しめるようにするためにダウンコンバートは重要な役割を担っています。動画ファイルの保存容量を小さくしたい場合にもダウンコンバートは有効です。高画質の動画ファイルは容量が非常に大きいため、保存できる数が限られてしまいます。ダウンコンバートで画質を落とすことで、ファイルサイズを小さくして多くの動画を保存することができます。一見画質を落とすだけの不要な作業に思えるかもしれませんが、実は様々な機器との互換性を保ち、多くの場面で動画を楽しむために必要不可欠な技術なのです。