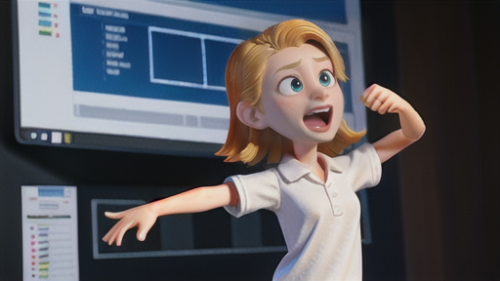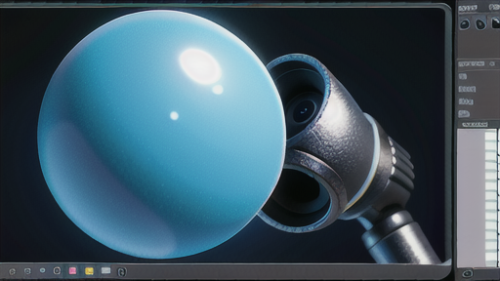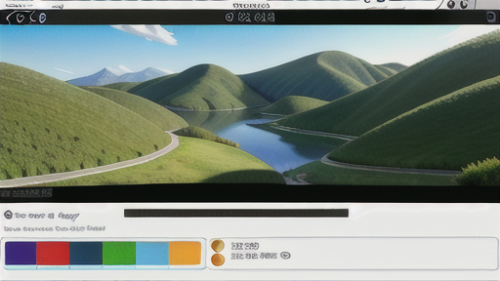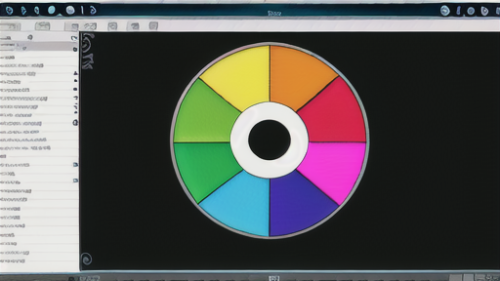撮影技術
撮影技術 動画制作:噛むことへの対処法
動画を作る上で、「噛む」とは、あらかじめ用意した台詞を正しく言えなかったり、滑らかに話せないことを意味します。視聴者の方々には小さな間違いに感じられるかもしれませんが、動画の見栄えに大きな影響を与えます。質の高い動画を目指すなら、噛むことは避けるべきです。話し手はアナウンサーや役者のように言葉のプロでない限り、一度の撮影で完璧に台詞を言うことは至難の業です。特に、長い台詞や難しい言葉を含む時は、噛みやすくなります。その他にも、緊張やプレッシャーも噛む原因になります。撮影機材の前で話すという状況が緊張を高め、普段は難なく話せる人でも、噛んでしまうことはよくあります。噛んでしまうと、動画の信頼性が損なわれる可能性があります。視聴者は、話し手が言葉に詰まったり、言い間違えると、内容の信ぴょう性を疑ってしまうかもしれません。また、動画の流れも途切れてしまい、視聴者の集中力を削いでしまう恐れもあります。質の高い動画制作には、事前の準備と練習が不可欠です。台詞をしっかりと覚え、発音やアクセントを確認し、何度も練習することで、噛むリスクを減らせます。さらに、撮影本番では、リラックスした状態で臨むことも重要です。深呼吸をする、周りのスタッフと談笑するなど、緊張をほぐす工夫を取り入れましょう。もし、撮影中に噛んでしまったとしても、慌てずに落ち着いてもう一度言い直せば大丈夫です。動画編集ソフトを使えば、後から噛んでしまった部分を修正することも可能です。完璧を目指すことは大切ですが、過度に緊張せず、自然な話し方を心掛けることが、最終的には良い結果に繋がります。