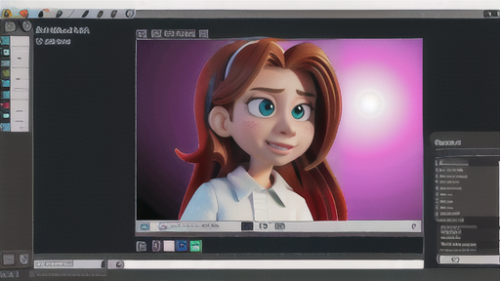画質
画質 プログレッシブ方式で動画の画質を高めよう
動画は、実はたくさんの静止画を連続して表示することで、動いているように見せているものです。パラパラ漫画を想像してみてください。一枚一枚の絵が少しずつ変化することで、絵が動いているように見えますよね。動画も同じ仕組みです。この静止画一枚一枚を画面に表示する方法を、走査方式といいます。走査方式には大きく分けて、プログレッシブ方式とインターレース方式の二種類があります。まず、インターレース方式について説明します。インターレース方式は、テレビ画面を横切る細い線を一本ずつ描いていくのですが、この線を走査線と呼びます。インターレース方式では、まず奇数番目の走査線、つまり1番目、3番目、5番目…というように線を描き、次に偶数番目の走査線、つまり2番目、4番目、6番目…というように線を描きます。つまり、画面全体を一度に描いているのではなく、画面を二回に分けて描いているのです。このようにして表示速度を優先した方式で、かつてはテレビ放送などで広く使われていました。しかし、動きの速い映像では線がずれて表示されてしまうという欠点がありました。一方、プログレッシブ方式は、1フレーム分の走査線を一度にすべて描画する方式です。つまり、画面全体を一回で描いているのです。インターレース方式に比べて描画に時間がかかりますが、画質が優れており、動きの速い映像でも線がずれることなく、くっきりと表示されます。そのため、現在ではパソコンやスマートフォン、高画質テレビなど、様々な場面で主流の方式となっています。このように、表示の仕方が異なる二つの走査方式ですが、それぞれに利点と欠点があります。技術の進歩とともに、より高画質で滑らかな動画が見られるようになってきており、今後ますます動画技術は発展していくことでしょう。