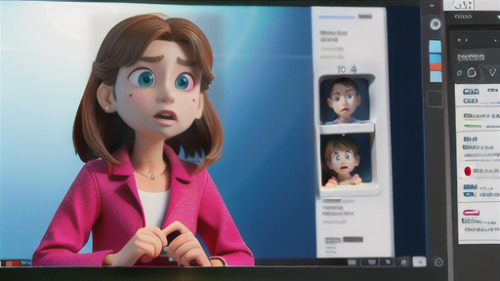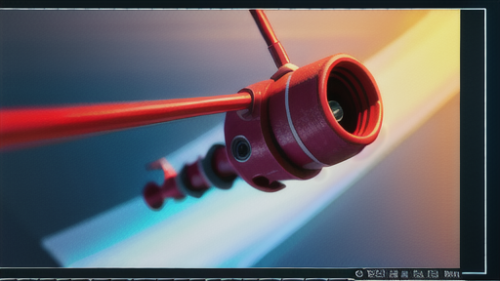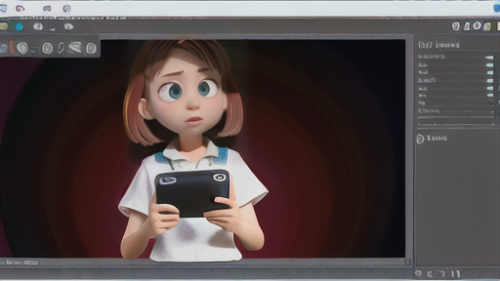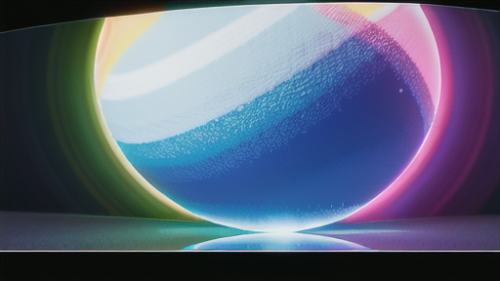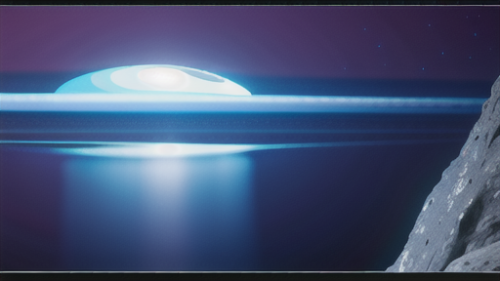コーデック
コーデック 動画圧縮の鍵、GOPを理解する
動画を取り扱う上で、どうしても避けることができないのがファイルサイズの大きさです。美しい高画質動画ほどファイルサイズは大きくなり、パソコンやスマートフォンといった機器の保存容量を圧迫するだけでなく、動画のやり取りにかかる時間も長くなってしまいます。そこで必要になってくるのが動画圧縮技術です。動画圧縮は、ファイルサイズを小さくすることでこれらの問題を解決し、誰でも気軽に動画を楽しめるようにするための大切な技術です。動画圧縮には様々な方法がありますが、共通して使われている考え方のひとつにGOP(グループ・オブ・ピクチャーズ)という仕組みがあります。これは、動画をいくつかのコマの集まり(グループ)に分けて、それぞれのグループの中で効率的にデータを減らす方法です。グループの中には、Iフレーム、Pフレーム、Bフレームと呼ばれる3種類のフレーム(コマ)があります。Iフレームは、グループの中で一番最初のフレームで、それ自体で完結した画像情報を持っています。いわば、一枚の絵のようなものです。そのため、他のフレームに比べてデータ量は多くなります。Pフレームは、Iフレームを基準にして、変化した部分の情報だけを持つフレームです。前のフレームとの違いだけを記録するので、データ量はIフレームより少なくなります。Bフレームは、前後のフレームを基準にして、変化した部分の情報だけを持つフレームです。これもデータ量は少なくなります。これらのフレームを組み合わせることで、全体的なデータ量を減らしつつ、高画質を維持することができます。例えば、風景がほとんど変わらないシーンでは、Iフレームを1枚作って、あとはPフレームやBフレームを使って変化した部分だけを記録すれば、データ量は大幅に削減できます。このように、GOPをうまく使うことで、動画のファイルサイズを小さくし、快適な動画視聴を実現することが可能になります。動画圧縮技術は日々進化しており、より高画質で小さなファイルサイズの動画を実現するための研究開発が盛んに行われています。動画圧縮は、動画配信や動画共有サービスなど、様々な場面で活用されており、私たちの動画視聴体験を支える重要な役割を担っています。