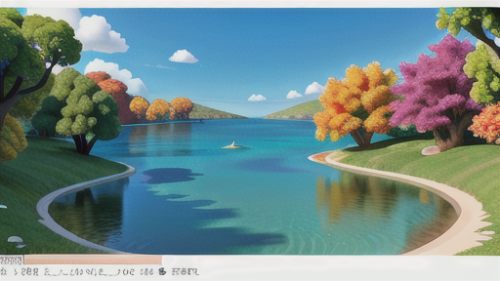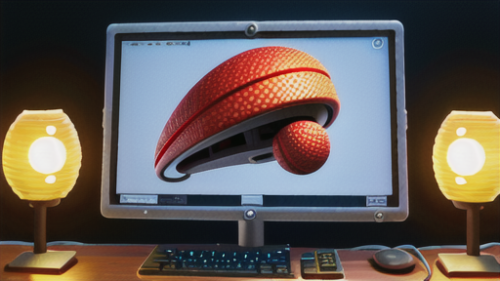音声
音声 DAT:デジタル録音の雄
デジタル音声テープ、略してDAT。かつて一世を風靡した、デジタル録音再生機です。見た目は、カセットテープとよく似た、小さな専用のテープを使います。しかし、中身は全くの別物。DATは、音をデジタル信号に変換して記録する、当時としては画期的な技術を採用していました。このデジタル化こそが、DATの最大の特徴であり、原音に限りなく近い、高音質を実現したのです。特に、音楽を作る現場では、DATの澄み切った音質はなくてはならないものとなりました。プロの技術者たちはこぞってDATを導入し、録音や編集作業に活用しました。かつての音楽スタジオでは、DATレコーダーが所狭しと並んでいた光景がよく見られました。録音した音を編集したり、加工したりする際にも、DATの音質の良さは大きなメリットとなりました。家庭用としても販売はされましたが、価格が高かったことが普及の妨げとなりました。加えて、より小型で手軽な、ミニディスク(MD)の登場により、DATは徐々に市場から姿を消していきました。手軽に持ち運べるMDは、若者を中心に爆発的に普及し、DATは太刀打ちできませんでした。しかし、時代は巡り、現在では、DAT本来の高い音質が見直されています。一部の音にこだわる愛好家の間で、DATは再び注目を集めており、中古市場では高値で取引されることも珍しくありません。デジタル技術が進歩した現代においても、DATの独特の音の温かみや深みは、他の機器では再現できないと評価されています。まさに、時代を超えて愛される名機と言えるでしょう。