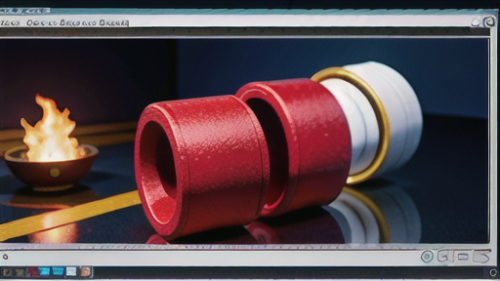規格
規格 W-VHS:高画質ビデオ時代の到来
1993年、家庭用ビデオの景色を一変させる出来事が起こりました。ビデオテープレコーダー、いわゆるVTRの世界に、日本ビクターから「W-VHS」という革新的な製品が登場したのです。それまでのビデオは、どうしても画像が粗く、現実世界をそのまま映し出すには限界がありました。特に動きが速い場面では、残像が残ったり、輪郭がぼやけたりするなど、画質の悪さが目立つことも少なくありませんでした。しかし、W-VHSは、従来のビデオ方式とは比べ物にならないほど高精細な映像を実現しました。W-VHSの秘密は、その名の通り、より広いテープ幅にありました。広いテープに多くの情報を記録することで、きめ細やかな映像を表現することが可能になったのです。これにより、まるでテレビ画面を通して現実世界を見ているかのような、驚くほど鮮明な映像が家庭で楽しめるようになりました。スポーツ番組の躍動感あふれるプレーや、自然の風景の繊細な色彩、人物の表情の微妙な変化など、これまで表現しきれなかった細部まで鮮やかに再現され、視聴者は画面に釘付けになりました。このW-VHSの登場は、家庭用ビデオの画質に対する意識を大きく変える出来事でした。人々は、より高画質で美しい映像を求めるようになり、ビデオメーカー各社も高画質化技術の開発にしのぎを削るようになりました。W-VHSは、まさに高画質ビデオ時代の幕開けを告げる、エポックメイキングな製品だったと言えるでしょう。