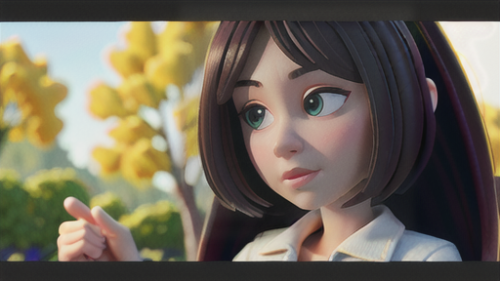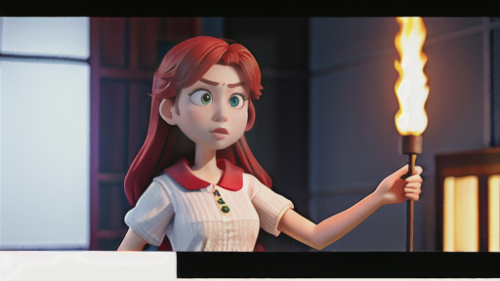規格
規格 ノン・ドロップフレームタイムコード詳解
動画を作る際に、時間をきちんと管理することはとても大切です。そこで活躍するのがノン・ドロップフレームタイムコードと呼ばれるものです。これは、動画の中の時間を正確に示すための大切な要素です。このタイムコードは、常に1秒間に30枚の画像(フレーム)があるものとして時間を数えます。実際に見えている時間も、タイムコードに表示されている時間も常にぴったり合っています。そのため、動画を編集したり、素材を管理したりする作業が簡単になります。ノン・ドロップフレームタイムコードは、フィルムではなく、ビデオやパソコンを使った編集で主に用いられます。パソコンは正確にフレームの数を数えるのが得意だからです。放送局やインターネットで動画を配信する際など、時間をぴったり合わせる必要がある時にも広く使われています。ノン・ドロップフレームタイムコードは、別名「フルフレーム」とも呼ばれます。これは、その名前の通り、全てのフレームを数えているからです。ですから、分かりやすく、直感的に理解しやすいという長所があります。例えば、30分の動画であれば、タイムコードは00300000と表示され、これは30分ちょうどであることを示しています。このように、ノン・ドロップフレームタイムコードは、動画制作において、時間の管理を容易にし、正確な編集作業を可能にする、なくてはならないものなのです。