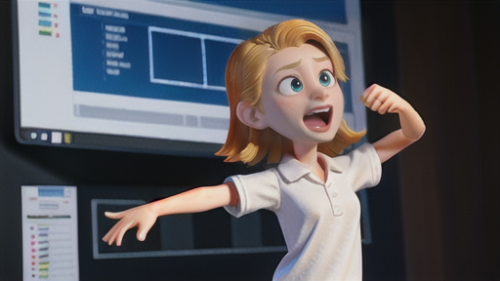 音声
音声 聞こえない音:可聴帯域外の世界
私たちは日常生活で様々な音を耳にしていますが、実際には、耳にしている音は全体の一部でしかありません。まるで、広大な宇宙の一部分だけを見ているようなものです。音の世界にも、私たちには見えない、聞こえない領域が存在します。人間の耳には聞こえる音の範囲があり、これを可聴範囲と言います。一般的には、低い音で20ヘルツ、高い音で2万ヘルツまでの範囲とされています。ヘルツとは、1秒間に何回空気が振動するかを表す単位で、この振動数が音の高さとして感じられます。20ヘルツは、大型トラックのエンジン音のような低い音をイメージすると分かりやすいでしょう。一方、2万ヘルツは、蚊の羽音のような非常に高い音です。人間の耳はこの範囲内の音を知覚することができます。しかし、この可聴範囲外の周波数の音も確かに存在します。これを可聴範囲外の音と呼びます。例えば、犬笛は人間には聞こえませんが、犬には聞こえる周波数の音を出しています。イルカやコウモリなども、人間には聞こえない超音波を使ってコミュニケーションをとったり、獲物の位置を把握したりしています。このように、音の世界は私たちが思っている以上に広く、多様なのです。さらに、可聴範囲は個人差や年齢によって変化します。特に加齢に伴い、高い音から聞こえにくくなる傾向があります。若い頃は聞こえていた高周波数の音が、年齢を重ねるにつれて聞こえにくくなるのはよくあることです。そのため、同じ音源を聞いていても、人によって聞こえ方が異なる場合があります。ある人には聞こえている音が、別の人には聞こえていないということもあるでしょう。聞こえるか聞こえないかの境界線は、実は一人ひとり異なり、曖昧なものなのです。








