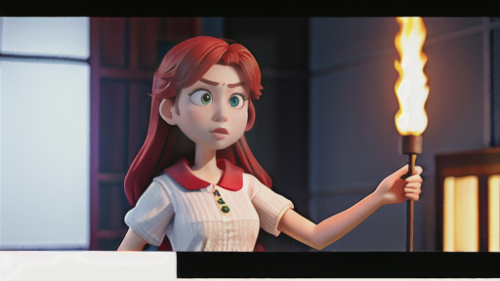規格
規格 インターレースとは?動画の仕組みを解説
昔のテレビ放送などでよく使われていた画面の描き方、インターレースについて説明します。正式にはインターレース走査と呼ばれ、細い線である走査線を画面全体に走らせて絵を描く方法です。インターレースでは、画面の走査線を奇数番目と偶数番目に分けます。まず、奇数番目の線だけを描いて、次に偶数番目の線を描きます。これを繰り返すことで、一枚の絵が完成します。まるで、田んぼに水を引くときのように、一本おきに線を引いていく様子を想像してみてください。なぜこのような方法が使われていたのでしょうか?それは、人間の目の性質と関係があります。人間の目は一度見た映像を少しの間覚えている性質があり、これを残像効果といいます。インターレースはこの残像効果を利用しています。奇数と偶数の線を交互に表示しても、残像効果のおかげで、人間の目には線が一本ずつ描かれているようには見えず、完全な絵として認識されます。インターレースの最大の利点は、少ない情報量で動画を表示できることです。画面全体を一度に描くよりも、半分ずつの情報で済むので、データの送る速さが遅くても動画を表示できます。昔のテレビ放送では、データを送る技術が今ほど発達していなかったので、この技術はとても役に立ちました。また、残像効果のおかげで、奇数と偶数の線を交互に表示しているにもかかわらず、画面がちらついて見えることもありません。まるで、パラパラ漫画をめくるように、高速で切り替わることで、滑らかな動きに見せているのです。インターレースは現在でも、古い形式のテレビ放送や一部の記録媒体で使われています。しかし、より高画質で滑らかな動画を表示するために、新しい技術も開発されています。