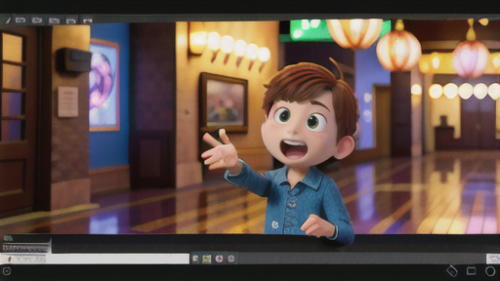動画編集
動画編集 動画編集の効率化:EDL活用術
動画を作る際に、編集決定一覧表はとても役に立ちます。これは、英語でEdit Decision Listと言い、頭文字をとってEDLと呼ばれています。動画編集の指示書のようなもので、編集作業を始める前に、どの部分をどのくらいの時間で使うか、どんな効果を加えるかなどを細かく書き記しておきます。例えるなら、家の設計図のようなものです。家を建てる前に設計図があれば、大工さんはその通りに作業を進めるだけで、迷うことなく家を完成させることができます。同じように、EDLがあれば、編集する人はその指示通りに作業を進めるだけで済みます。EDLを使うメリットはたくさんあります。まず、編集作業が速くなります。次に、編集に関わる人たちの間で、完成イメージを共有しやすくなるので、意思の食い違いを防ぐことができます。さらに、編集作業を始める前に全体像を把握できるため、完成形を想像しやすく、後から修正する手間も省けます。例えば、複数人で動画を作る場合、EDLがあれば、誰が編集を担当しても同じように作業を進めることができます。また、クライアントに完成イメージを伝える際にも、EDLを見せることで、具体的なイメージを共有することができ、修正の指示もスムーズになります。このように、EDLは動画編集の質を高め、作業を効率化するための、大切な道具と言えるでしょう。