動画の基礎: フレームについて

動画を作りたい
先生、『フレーム』って言葉がよくわかっていないんですけど、教えてもらえますか?

動画制作専門家
もちろん!簡単に言うと、動画はパラパラ漫画のようにたくさんの絵が連続して表示されることで動いて見えるよね。その一枚一枚の絵のことを『フレーム』と呼ぶんだよ。

動画を作りたい
パラパラ漫画みたいなものなんですね!なんとなくわかりました。一枚の絵ってことは、動画は何枚ものフレームが繋がっているということですか?

動画制作専門家
その理解でいいね。例えば、1秒間に30枚のフレームを表示すると、30fps(フレーム毎秒)の動画になる。フレームが多いほど、滑らかな動きになるんだよ。
frameとは。
動画を作る上で『こま』と呼ばれる用語について説明します。テレビの映像は、たくさんの細い線で描かれています。NTSC方式という方法では、525本の線を使って1つの画面を作ります。この画面のことを『こま』と言います。インターレース方式という方法では、2つの画面を組み合わせて1つの『こま』を作ります。
動画とコマの関係

動画は、実はたくさんの絵が連続して表示されることで動いているように見せているものです。この絵のことを「こま」と呼びます。パラパラ漫画を思い浮かべてみてください。パラパラ漫画は、少しだけ違う絵が描かれた紙を何枚も重ね、それを素早くめくることで、絵が動いているように見せるものです。動画もこれと同じ仕組みで、一枚一枚のこまを高速で切り替えることで、滑らかで自然な動きを作り出しているのです。
このこま一枚一枚は、動画の中では「フレーム」とも呼ばれます。動画はこのフレームを基本単位として構成されており、フレームの数が多ければ多いほど、動画は滑らかに見えます。パラパラ漫画を例に挙げると、一枚の絵と次の絵の変化が小さければ小さいほど、めくった時により滑らかに動いて見えますよね。動画も同じで、フレームレートと呼ばれる、1秒間に表示されるフレームの数が多ければ多いほど、より滑らかで自然な動きを表現できるのです。
例えば、テレビのニュース番組やスポーツ中継など、動きが激しい映像では、通常1秒間に30枚のこまが使われています。これは30fps(フレーム毎秒)と表現されます。一方、映画では1秒間に24枚のこまが使われることが多く、24fpsと表現されます。このように、動画の種類や用途、表現したい動きによって、最適なフレームレートは異なってきます。
つまり、動画を作る上で、こま、つまりフレームを理解することはとても重要です。フレームレートを調整することで、動画の滑らかさを変えたり、特殊な効果を生み出したりすることもできます。動画制作を始めるにあたって、まずはフレームという概念をしっかりと理解しておきましょう。そうすることで、より質の高い動画制作が可能になります。
| 動画の構成要素 | 説明 | 動画への影響 |
|---|---|---|
| こま(フレーム) | 動画を構成する一枚一枚の絵。 | フレーム数が多ければ多いほど、動画は滑らかに見える。 |
| フレームレート(fps) | 1秒間に表示されるフレームの数。 | フレームレートが高ければ高いほど、より滑らかで自然な動きを表現できる。動画の種類や用途、表現したい動きによって最適なフレームレートは異なってくる。 |
コマの仕組み

動画は、実はたくさんの静止画が連続して表示されることで、動いているように見えています。この静止画一枚一枚を「コマ」と呼びます。コマ送りのように、パラパラ漫画を想像すると分かりやすいでしょう。一枚一枚の絵がわずかに変化することで、動いているように見えるのと同じ仕組みです。
では、このコマはどのようにして画面に表示されるのでしょうか。昔ながらのブラウン管テレビを例に考えてみましょう。ブラウン管テレビの中には電子銃と呼ばれる装置があり、そこから電子ビームという光線のようなものが発射されます。この電子ビームが、テレビ画面に塗られた特殊な塗料に当たると、塗料が光ります。電子ビームは、画面の左上から右下へ、一行ずつ線を引くように動いていきます。この線を走査線と呼びます。走査線は、まるで筆で絵を描くように、画面全体をくまなく照らしていきます。一本の走査線だけでは何も見えませんが、たくさんの走査線が重なり合うことで、一つの絵、つまり一つのコマが完成します。
例えば、日本のテレビ放送で使われていた仕組みの一つである「NTSC方式」では、525本の走査線を使って一つのコマを描いていました。525本もの線が、上から下へと順番に描かれ、一つの画面を作り上げます。このコマが、一秒間に数十回という速さで次々と切り替わることで、私たちは動画として認識しているのです。まるで、パラパラ漫画をめくる速さをとても速くしたようなものです。コマが切り替わる速さは、動画の滑らかさに関係します。コマ数が多ければ多いほど、滑らかな動画になります。
このコマの仕組みを理解することは、動画の画質や表示方法について深く理解する上でとても大切なことです。画面の大きさや鮮やかさといった要素も、このコマの仕組みと密接に関係しています。コマという小さな単位が、どのようにして動画を作り上げているのかを知ることで、動画の見え方が変わってくるかもしれません。
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| コマ | 動画を構成する一枚一枚の静止画。 |
| 電子銃 | ブラウン管テレビの中で電子ビームを発射する装置。 |
| 電子ビーム | 電子銃から発射される光線のようなもの。画面の塗料に当たると光る。 |
| 走査線 | 電子ビームが画面上を走査する線。筆で絵を描くように画面全体を照らす。 |
| NTSC方式 | 日本のテレビ放送で使われていた方式の一つ。525本の走査線を使って一つのコマを描く。 |
飛び越し走査について

動画は、まるでパラパラめくりのように、たくさんの静止画を連続して表示することで動いているように見せています。この静止画一枚一枚をフレームと呼びます。画面を構成する細かい横線は走査線と呼ばれ、この走査線をどのように描いていくかという方法を走査方式と言います。
飛び越し走査は、インターレース方式とも呼ばれる走査方式で、かつてテレビ放送でよく使われていました。この方式の特徴は、一つのフレームを描くのに二つの行程に分けて行うところにあります。まず、奇数番目の走査線だけを上から順番に描いていきます。これを最初のフィールドと呼びます。次に、偶数番目の走査線だけを同じように上から順番に描いていきます。これが二番目のフィールドです。そして、この二つのフィールドを組み合わせることで、一つの完全なフレームが作り出されるのです。
例えるなら、一枚の絵を完成させるために、まず奇数番目の横線だけを描き、次に偶数番目の横線を描くようなものです。二つのフィールドを組み合わせることで、最終的に全体像が浮かび上がってきます。
なぜこのような複雑な方法が使われていたのでしょうか。それは、当時の技術的な制約に理由があります。一度に全ての走査線を描くには、当時の機器の処理能力では難しかったのです。そこで、走査線を半分ずつ描くことで、必要な情報を減らし、画面を更新する速度、つまりフレームレートを高く見せる工夫がなされていました。少ない情報で動きの滑らかさを実現していたと言えるでしょう。
現在では、プログレッシブ方式という、全ての走査線を一度に描く方式が主流となっています。プログレッシブ方式では、ちらつきなども少なく、より鮮明な映像を見ることができます。しかし、インターレース方式の歴史を知ることは、動画技術がどのように進化してきたかを理解する上で非常に重要です。
コマ数と動画の滑らかさ

動画の滑らかさは、1秒間に流れる絵の数(コマ数)で決まります。このコマ数を専門用語で「フレームレート」と呼び、単位は「fps」(フレーム毎秒)で表します。つまり、フレームレートが高いほど、1秒間に多くの絵が流れ、動画は滑らかに見えるのです。
身近な例で考えてみましょう。映画は通常24fpsで撮影・上映されています。これは、1秒間に24枚の絵が切り替わるということです。一方、テレビ放送では30fps、最近のテレビゲームなどでは60fps以上が一般的です。これらの数字を比べると、なぜゲームの映像がテレビ放送や映画よりも滑らかに見えるのかが理解できるでしょう。
フレームレートが低いと、動画はカクカクとした印象になります。古い映画を見ると、どこかぎこちなく感じるのは、24fpsという比較的低いフレームレートによるものです。技術的な制約からコマ数が少なかった時代の映像は、どうしても滑らかさに欠けてしまうのです。現代の技術では、さらに高いフレームレートでの撮影が可能になり、120fpsや240fpsで撮影された映像は、非常に滑らかで、現実世界を見ているかのような錯覚を覚えるほどです。
スポーツ中継などで見かけるスローモーション映像も、このフレームレートと深く関係しています。スローモーションは、高フレームレートで撮影した映像を、再生速度を遅くすることで実現します。例えば、120fpsで撮影した映像を30fpsで再生すると、4倍のスローモーションになります。コマ数が多ければ多いほど、再生速度を遅くしても滑らかなスローモーション映像を作ることができるのです。このように、フレームレートは動画の見え方に大きな影響を与える重要な要素と言えるでしょう。
| フレームレート(fps) | 動画の見え方 | 用途例 |
|---|---|---|
| 24 | ややカクカクした印象 | 映画 |
| 30 | 比較的滑らか | テレビ放送 |
| 60以上 | 非常に滑らか | テレビゲーム |
| 120, 240 | 非常に滑らか、現実世界のような錯覚 | 高品質映像 |
コマとデータ量
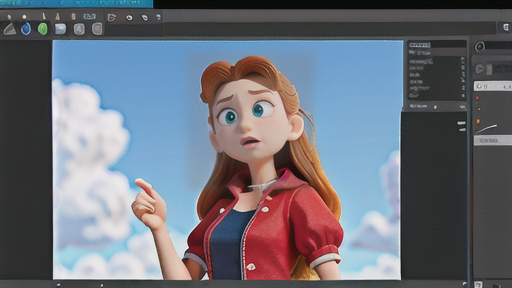
動画の滑らかさは、コマ数、つまり1秒間に表示される静止画の数で決まります。このコマ数を専門用語で「フレームレート」と呼び、単位は「fps(フレーム毎秒)」で表します。例えば、30fpsであれば、1秒間に30枚の静止画が連続して表示されることを意味します。
フレームレートが高いほど、動画は滑らかに見えますが、同時にデータ量も増加します。なぜなら、フレームレートが高いということは、1秒間に処理しなければならない画像情報が多くなるからです。1枚の絵を想像してみてください。その絵を30枚用意するのと、60枚用意するのとでは、どちらが多くの情報量を持っているでしょうか?当然、60枚の方ですね。動画も同じで、フレームレートが高いほど、多くの情報が含まれるため、ファイルサイズが大きくなります。
大きなファイルは、保存する場所を多く必要とします。パソコンやスマートフォン、動画投稿用の場所など、保存できる量には限りがあります。大きなファイルをたくさん保存すると、すぐに容量がいっぱいになってしまいます。また、ファイルサイズが大きいと、動画の読み込みに時間がかかり、再生開始までに待たされることもあります。場合によっては、読み込みが追いつかず、再生が途切れてしまう可能性も出てきます。
そのため、動画を作る際には、フレームレートとデータ量のバランスを考えることが大切です。高画質で滑らかな動画にしたい場合は、高いフレームレートを選ぶ必要がありますが、ファイルサイズが大きくなることを念頭に置かなければなりません。動画投稿場所に投稿したり、誰かと共有したりする場合は、適切なフレームレートを選ぶことで、データ量を抑えつつ、見る人に快適に視聴してもらうことができます。例えば、動きが激しい場面は高いフレームレートにし、そうでない場面は低いフレームレートにするなど、工夫次第でデータ量を調整することも可能です。
| フレームレート | メリット | デメリット | その他 |
|---|---|---|---|
| 高 (例: 60fps) | 動画が滑らかに見える | データ量が増加し、ファイルサイズが大きくなる 保存容量を多く必要とする 読み込みに時間がかかる場合がある 再生が途切れる可能性がある |
動きが激しい場面に適している |
| 低 (例: 30fps) | データ量を抑えることができる ファイルサイズが小さくなる 読み込みが速い 保存容量を節約できる |
動画が滑らかに見えない場合がある | 動きが少ない場面に適している |
