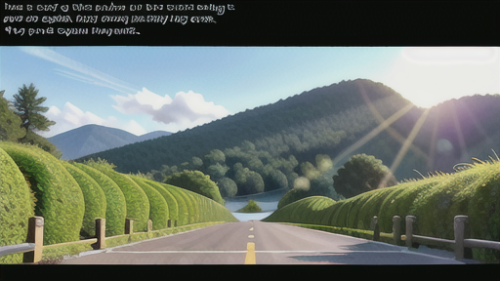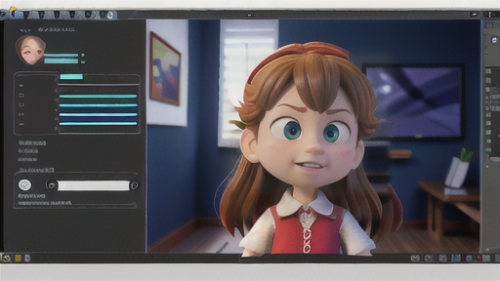音声
音声 基準信号で調整!アライメントテープ徹底解説
音声を記録して再びそれを聞く機械、特に箱型の音楽用テープや、大きな巻き取り式のテープを使う機械は、小さな部品の組み合わせでできています。これらの部品がうまく動くことで、良い音で記録したり聞いたりすることができます。しかし、長い間使っていたり、使う回数が多いと、周りの環境なども影響して、部品が古くなったり、ずれたりすることがあります。そこで、特別な調整用テープを使って、テープを動かす部分を調整する必要があります。これは楽器の音を合わせる作業によく似ています。正しい調整を行うことで、記録した音がゆがむことなく、きれいに聞こえるようになり、本来の音質を楽しむことができます。調整用テープには、色々な音や信号が記録されています。このテープを再生しながら、機械のネジなどを回し、音を聞きながら調整していきます。例えば、高い音と低い音のバランスや、左右の音量、音の伸び具合などを調整します。この作業は、機械によって調整箇所や手順が違います。説明書をよく読んで、慎重に行う必要があります。調整がうまくいかないと、音が悪くなるばかりか、機械を壊してしまうこともあります。自信がない場合は、詳しい人に頼むのが良いでしょう。最近は、こういった機械を使う人が少なくなりましたが、きちんと調整された機械で聞く音は格別です。古い録音も、生き生きとした音で蘇ります。ぜひ、この機会に調整に挑戦してみてはいかがでしょうか。