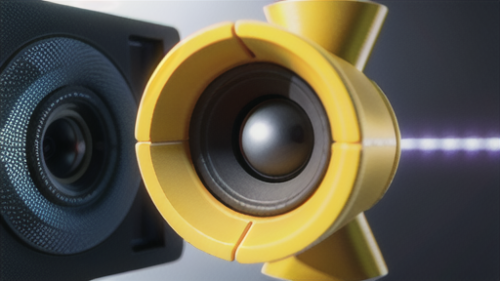規格
規格 SHOWSCAN:究極の映像体験
ショウ・スキャンといえば、何と言ってもその滑らかな映像が最大の特徴です。普段私たちが映画館で見ている映画は、一秒間に二十四枚の絵を繋げて動きを表現しています。しかしショウ・スキャンは、一秒間に六十枚もの絵を使って映像を作り出しているのです。これは一般的な映画の二倍半にあたります。一枚一枚の絵が変わる速さが速ければ速いほど、映像は滑らかに見えます。逆に枚数が少なければ、どうしても絵と絵の繋ぎ目が目立ち、動きがカクカクして見えてしまうことがあります。ショウ・スキャンでは、この絵の枚数を増やすことで、まるで現実世界を見ているかのような滑らかな映像を実現しました。特に、動きの激しい場面でその効果は絶大です。例えば、カーチェイスのシーンを想像してみてください。普通の映画では、スピード感あふれる場面でも、どこかぎこちなく感じてしまうことがあるかもしれません。しかしショウ・スキャンなら、車の動きや風景の変化が驚くほど滑らかに表現されるので、まるで自分が実際に車に乗っているかのような、スピード感と臨場感を味わうことができるのです。この滑らかな映像は、ショウ・スキャンならではの魅力と言えるでしょう。まるで現実の出来事を目の前で見ているかのような感覚は、他の映画では味わえない特別な体験です。この技術によって、映画の世界にさらに深く入り込み、物語をよりリアルに感じることができるようになります。一秒間に六十枚の絵が織りなす、滑らかで自然な映像美を、ぜひ一度体験してみてください。