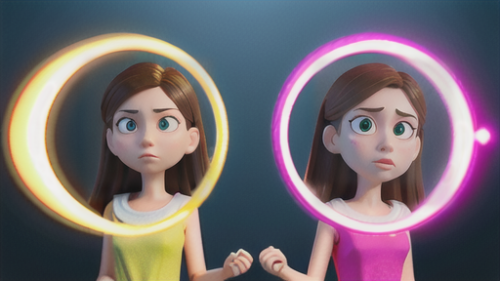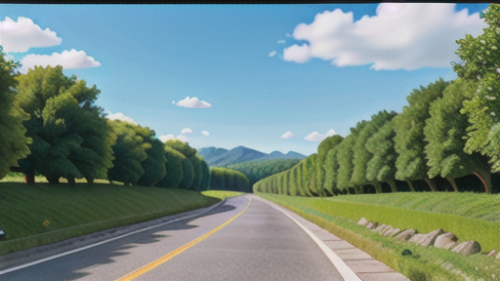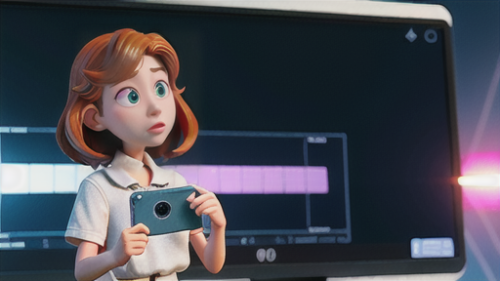動画編集
動画編集 動画制作の要、オペークとは?
動画を作る上で、文字を映像に重ねることは欠かせません。かつて、この大切な役割を担っていたのが、文字重ね合わせ装置です。今ではコンピューターで簡単にできますが、以前は専用の装置が必要でした。この装置は、情報番組の速報や番組の題名、会社の印などを表示するために使われていました。文字重ね合わせ装置は、専用の板に文字や絵を描き、それを装置に読み込ませることで、映像に合成する仕組みでした。この板は文字板と呼ばれ、様々な字形や大きさ、色を使って文字を表現できました。たとえば、毛筆のような字形や、明朝体、ゴシック体など、多様な表現が可能でした。大きさも自由に調整でき、小さな文字から大きなまで、用途に合わせて使い分けることができました。また、色も自由に設定でき、赤や青、黄色など、様々な色で文字を表示できました。この文字板は、手書きで作成することもできました。そのため、急に内容を変更する必要が生じた場合でも、素早く対応することができました。生放送中に情報が更新された時などは、この機能が大変役に立ちました。文字重ね合わせ装置は、編集機とは別の独立した機械として存在していました。編集機に信号を送ることで、映像に文字を重ねて表示させていました。この装置のおかげで、視聴者は映像と共に文字情報を受け取ることができ、内容をより深く理解することができました。まさに、動画に文字情報を加えるための、なくてはならない装置だったと言えるでしょう。