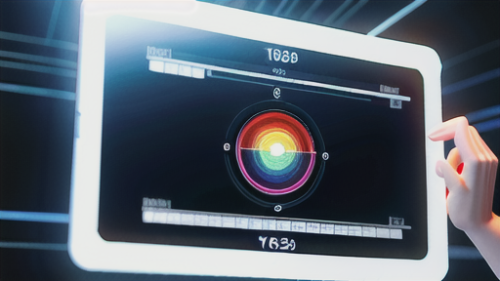映像エフェクト
映像エフェクト 動画制作における3D技術の活用
奥行きや立体感を表現した映像、それが三次元映像、つまり3Dと呼ばれるものです。普段私たちが見るテレビやパソコンの画面に映る映像は二次元映像と呼ばれ、平面的に見えます。これに対し、三次元映像は現実世界と同じように奥行きや立体感を感じることができ、まるで映像の中に入り込んだかのような体験ができます。この三次元映像は、特別な眼鏡を使うことで立体的に見えます。この眼鏡は、右目と左目に入る光をそれぞれ変えることで、脳をだまして立体感を作り出しています。右目と左目では見ている景色が少し違いますよね。この違いが、脳が奥行きを認識するもとになっているのです。三次元映像では、この仕組みを人工的に作り出し、右目と左目に微妙に違う映像を見せています。すると、脳はそれを実際の奥行きと勘違いし、立体的に感じてしまうのです。近年、この三次元映像技術は映画館でよく見られます。迫力のある映像で、まるで映画の世界に入り込んだような体験ができます。また、家庭用ゲーム機でも三次元映像を楽しむことができ、よりリアルなゲーム体験が可能になりました。さらに、広告の世界でも三次元映像は注目されており、商品をより魅力的に見せるために活用されています。このように三次元映像は様々な分野で活用されており、私たちの生活をより豊かで楽しいものにしてくれています。今後ますます技術が進化し、よりリアルで没入感の高い三次元映像体験が期待されます。