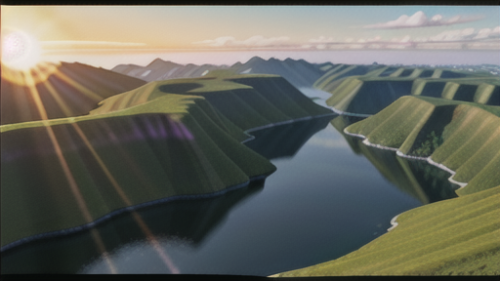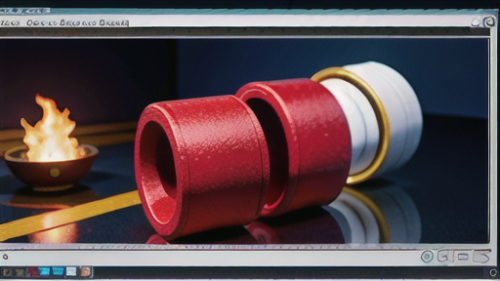音声
音声 音量の頂点を捉える:ピークレベルメーター
かつて、音の大きさを測る道具といえば、ブイユーメーターが主流でした。このメーターは、人の耳で聞いたときの音の大きさの変化と似たような表示をするのが得意で、音楽全体の大きさを知るには最適な道具でした。ゆったりとした曲調の変化や、全体的な音のバランスを掴むのにとても役立ち、多くの技術者に愛用されました。しかし、瞬間的に大きな音、例えば太鼓や打楽器の鋭い音には、このメーターはうまく反応できませんでした。メーターの針が動く速さが、速い音の変化に追いついていけないためです。そのため、録音時にこれらの音が割れてしまわないように、技術者は経験と勘を頼りに音の大きさを調整する必要がありました。針が振り切らないように、少し余裕を持たせて音を小さくしたり、音割れしないギリギリの音量を探ったりと、様々な工夫が凝らされていました。まるで職人のように、長年の経験と研ぎ澄まされた感覚で、絶妙なバランスを保っていたのです。しかし、このような経験と勘に頼った調整は、人によって差が出やすく、常に安定した音質を保つことが難しいという問題がありました。また、新しい技術者がすぐに技術を習得することも困難でした。そこで登場したのがピークレベルメーターです。この新しいメーターは、瞬間的な大きな音も正確に捉えることができるため、これまで経験と勘に頼っていた調整を数値化し、より正確な音量管理を可能にしました。音割れを防ぎながら、最大限の音量を確保することができるようになったため、音質の向上に大きく貢献しました。また、経験の浅い技術者でも一定水準の音量管理ができるようになったことで、技術の継承も容易になりました。ピークレベルメーターの登場は、録音技術における大きな進歩と言えるでしょう。