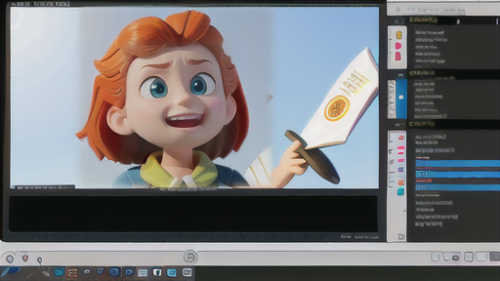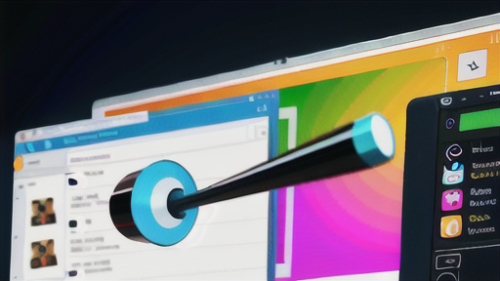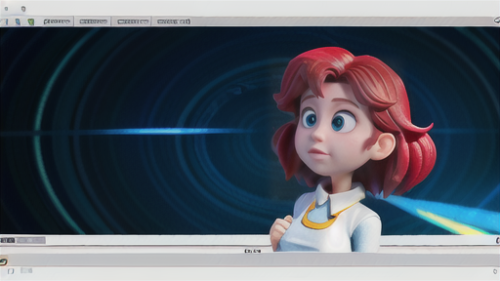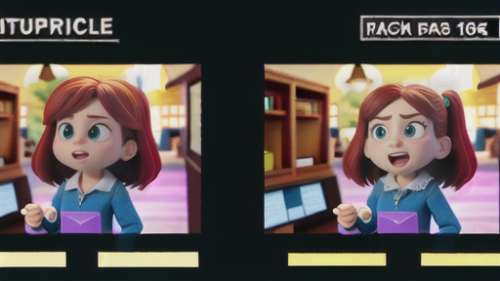音声
音声 チェイスモード:映像と音声の同期
動画を組み立てる場面で、音声と映像をぴったり合わせる作業はとても大切です。音と映像がずれていると、見ている人は違和感を覚えます。特に、セリフと口の動きが合っていないと、見ている人は内容に集中できません。チェイスモードは、この音と映像のずれを解消する技術です。別々に録音した音声を映像に合わせる時などによく使われます。チェイスモードは、複数の録画機材を連動させる「テープ同期方式」という仕組の中で働きます。この仕組では、基準となる映像を記録した機器を「親機」、合わせる映像を記録した機器を「子機」と呼びます。それぞれの機器には、録画した時間情報を示す「時間印」が記録されます。チェイスモードでは、子機の時間印が親機の時間印と同じになるように調整することで、音と映像を同期させます。具体的には、子機は親機の時間印を常に「追いかける」ように動きます。親機がある時間印の位置まで進むと、子機も同じ時間印の位置まで早送りしたり、巻き戻したりします。そして、親機と同じ時間印の位置で再生を始め、その後は親機と同じ速さで再生を続けます。まるで子機が親機の後を追いかけるように動くことから、「チェイスモード」という名前がつきました。この技術のおかげで、音と映像がぴったり合った、自然な動画を作ることができます。例えば、ドラマや映画の撮影で、俳優のセリフと口の動きをぴったり合わせたり、音楽番組で演奏と歌声を正確に同期させたりする際に、チェイスモードは欠かせない技術となっています。今ではデジタル技術の進化により、チェイスモードを使わずに音と映像を同期させる方法もありますが、チェイスモードは今でも正確で信頼性の高い同期方法として使われています。