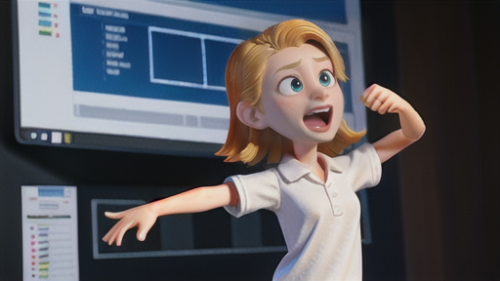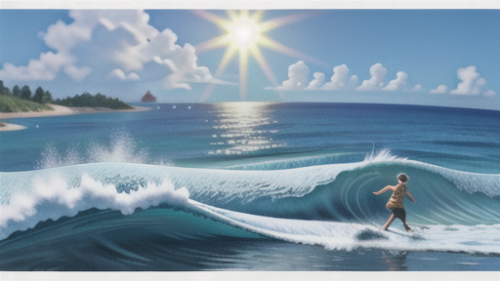インターネット
インターネット 動画配信を支える縁の下の力持ち:WEBサーバー
動画を画面で見られるようにする仕組みは、いろいろな技術がつながってできています。インターネットにつながった機器で動画を見たい時、まず動画サイトを開きます。すると、その機器は動画のデータを送ってくれるところに「この動画が見たいです」というお願いを送ります。このお願いを受け取ったところは「応答」として動画データを返します。このやり取りはまるで手紙のやり取りのようです。お願いの手紙を受け取ったら、返事の手紙を送るようなものです。動画データを受け取った機器は、それを再生して画面に映し出します。こうして私たちは動画を見ることができるのです。この動画データを送ってくれるところを「ウェブサーバー」と呼びます。ウェブサーバーは、インターネット上に作られた大きな図書館のようなものです。たくさんの情報を保管していて、必要な情報をすぐに取り出して送ってくれます。動画配信では、このウェブサーバーが動画データを保管し、私たちが見たい時にすぐに送ってくれる大切な役割を果たしているのです。動画データはそのままでは大きすぎるため、小さくして送る工夫もされています。また、たくさんの人が同時に同じ動画を見ようとすると、ウェブサーバーに負担がかかってしまいます。そこで、複数のウェブサーバーで役割を分担したり、近い場所に置いておくことで、スムーズに動画を見られるようにしているのです。まるで、図書館にたくさんの人が押し寄せても混乱しないように、司書を増やしたり、分館を各地に作るようなものです。このように、見えないところで様々な工夫が凝らされ、私たちは快適に動画を楽しめているのです。