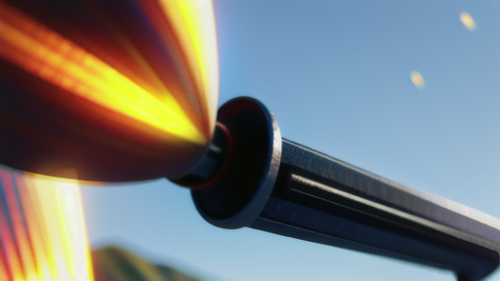規格
規格 家電連携の規格:HAViとは?
近頃は、身の回りの電化製品が、それぞれ単独で動くだけでなく、互いにつながり合って、より暮らしやすい環境を作ってくれるようになってきました。例えば、外出先からスマートフォンでエアコンをつけたり、冷蔵庫の中身を確認したりといったことが、すでに現実のものとなっています。このような、複数の機器が連携して動くためには、共通のことばで情報をやり取りするための規格が欠かせません。さながら、異なる国の人々が円滑に意思疎通をするために、共通の言語が必要となるのと同じです。今回ご紹介するHAVi(ホーム・オーディオ・ビデオ相互運用性)は、まさに家電製品同士が円滑に連携するための共通語と言えるものです。これは、家庭内のオーディオ機器や映像機器を中心とした電化製品が、メーカーの壁を越えて、互いに連携できるようにするための規格です。HAVi対応機器であれば、たとえ異なるメーカーの製品であっても、簡単に接続して連携動作させることができます。例えば、あるメーカーのテレビと、別のメーカーの録画機器をHAViで接続すれば、テレビのリモコンで録画機器の操作ができるようになったり、テレビ画面に録画機器のメニューを表示させたりすることが可能になります。HAViを知ることで、家電製品を選ぶ際の視点も大きく変わってくるでしょう。単に製品の機能や価格だけでなく、HAVi対応かどうかを確認することで、将来的な機器の拡張性や連携の可能性を考慮した、より賢い製品選びができるようになります。HAVi対応機器を揃えることで、より快適で便利な住環境を構築できます。例えば、照明やエアコン、カーテンなどをHAViで連携させれば、外出先からスマートフォンで家の状態を管理したり、帰宅時間に合わせて自動的に家電を起動させたりといった、一歩進んだ暮らしを実現することも夢ではありません。家電製品選びにHAViという視点を加えることで、未来のスマートホームへの第一歩を踏み出しましょう。