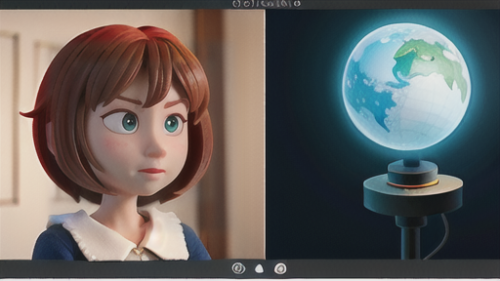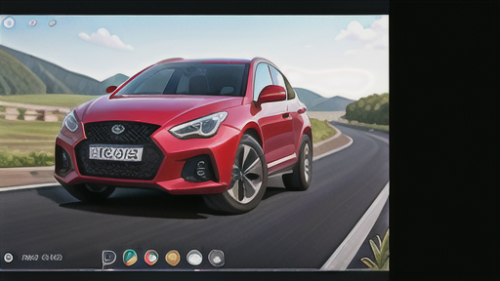音声
音声 アフレコ:動画制作の強力な武器
動画作りにおいて、絵と音は切っても切り離せない関係にあります。優れた映像に質の高い音が加わることで、見る人に深い感動を与えることができます。これまで、動画を作る際には、絵と同時に音も記録するのが一般的でした。しかし、周りの物音や話す人の緊張など、様々な理由で思い通りの音を録るのは難しいものでした。そこで近年注目されているのが『アフレコ』という手法です。アフレコとは、先に絵を記録しておき、それを再生しながら、画面に合わせて音を録音する方法です。この方法を使うことで、より鮮明で質の高い音を手に入れ、動画全体の出来栄えを良くすることができます。周りの雑音が入っていない、聞き取りやすい音は、見る人の理解を深め、動画の世界に引き込む上でとても大切です。例えば、屋外で撮影した動画の場合、風の音や街の喧騒など、様々な騒音が混じってしまうことがあります。アフレコなら、静かな場所で録音することで、これらの騒音を気にすることなく、クリアな音声を収録できます。また、出演者のセリフが噛んでしまったり、言い間違えてしまったりした場合でも、アフレコなら後で修正が可能です。部分的に録り直すことができるため、何度も最初から撮影し直す必要がなく、時間と労力の節約にも繋がります。アフレコは、動画の質を高めるだけでなく、制作の効率化にも貢献する、まさに動画と音声の新たな関係を築く、画期的な手法と言えるでしょう。ナレーションや効果音、BGMなども後から自由に付け加えることができ、表現の幅も広がります。より多くの人に見てもらうための動画作りにおいて、アフレコは今後ますます重要な役割を担っていくと考えられます。