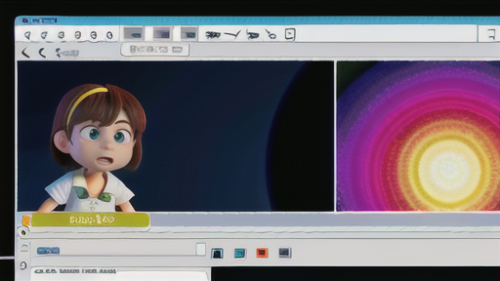音声
音声 録音の雑音:かぶりの影響と対策
{録音の良し悪しを左右する}「かぶり」とは、目的の音以外の余計な音がマイクに入り込んでしまう現象を指します。まるで薄い幕がかかったように聞きたい音が不明瞭になることから、このように呼ばれています。具体例を挙げると、歌手の歌声を録音する場面を考えてみましょう。歌声だけでなく、伴奏の楽器の音や空調の音、外の車の音、さらにはマイクの設置場所が悪ければ衣擦れの音まで拾ってしまうかもしれません。これら全てが「かぶり」にあたります。録音現場では様々な音が発生しており、マイクは指向性(特定の方向からの音を拾いやすい性質)を持っているとはいえ、完璧に目的の音だけを捉えることは難しいです。特に、繊細な音も拾い上げる高感度マイクは、かぶりが起こりやすい傾向があります。性能が良いが故に、周囲の音も拾いやすいという側面があるのです。この「かぶり」は、録音後の編集作業にも大きな影を落とします。録音した音源の不要な音を消したり、聞きたい音を際立たせる作業を「音の編集」と言いますが、かぶりが酷いと、聞きたい音が他の音に埋もれてしまい、音の編集が困難になります。雑音を取り除こうとすると、聞きたい音まで一緒に消えてしまう、といった具合です。結果として、クリアで聞き取りやすい音源を作るのが難しくなります。かぶりを完全に無くすことは難しいですが、録音時の工夫で最小限に抑えることは可能です。例えば、マイクと音源の距離を近づける、指向性の強いマイクを使う、周囲の雑音を減らすなど、様々な対策があります。録音環境を整えることで、クリアな音源を収録することが可能になります。