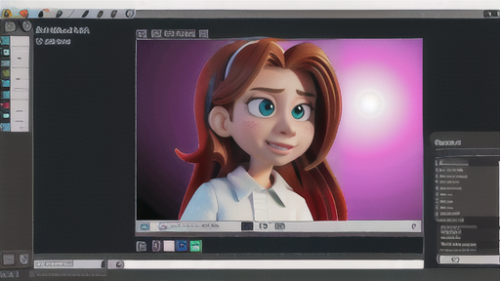画質
画質 動画と直線性:自然な表現を追求する
まっすぐな線のように、入力と出力の関係が一定であることを、直線性といいます。たとえば、かさを回して水道の水量を調節する様子を思い浮かべてみてください。かさを2倍回せば、水量も2倍になります。もし、かさを少し回しただけで水量が急激に増えたり、逆にたくさん回しても水量があまり変わらなかったりすると、使いづらいでしょう。動画制作においても、この直線性は大切な役割を担っています。カメラで捉えた光の量と、最終的に画面に映し出される明るさの関係が、直線性を持っていることが理想です。たとえば、撮影時の光の量が2倍になれば、画面の明るさも2倍になるといった具合です。もし、この関係が直線的でないと、映像は不自然に見えてしまいます。例えば、明るい部分が白く飛んでしまったり、暗い部分が黒くつぶれてしまったりする現象が起こります。白い壁に当たる日光や、木陰にできた影など、本来であれば豊かな階調で表現されるべき部分が、白や黒一色で塗りつぶされてしまうのです。このような映像は、現実の光景とは異なった印象を与え、視聴者に違和感を抱かせてしまうかもしれません。直線性を保つことで、撮影したままの自然な明るさ、暗さを再現することができます。明るい部分も暗い部分も、細やかな階調を表現することで、視聴者は制作者が伝えたいそのままの映像を、違和感なく見ることができるのです。これは、自然で美しい映像表現には欠かせない要素と言えるでしょう。まるで窓を通して景色を見ているかのような、ありのままの映像表現を可能にするのが、直線性なのです。