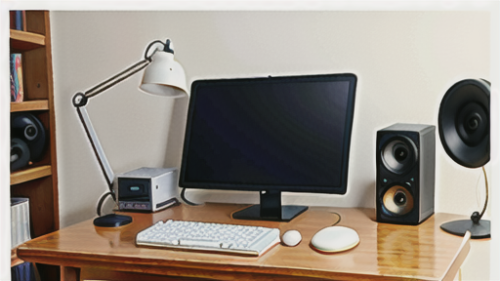音声
音声 クリッピング歪み:音質劣化の要因
音声や音楽を扱う上で、「ひずみ」は音質を大きく損なう悩みの種です。その中でも「切り取りひずみ」は、特に気を付けなければならないもののひとつです。一体どんなひずみで、なぜ起こるのでしょうか?それを紐解きながら、対策方法も考えてみましょう。切り取りひずみは、音の波形が本来描くべき形から、まるで刃物で切り取られたかのように平らになってしまう現象です。音の信号は、空気の振動を電気信号に変換したものですが、この電気信号の大きさが機器の処理できる範囲を超えてしまうと、それ以上大きな信号として記録することができなくなります。これが、波形が平らになってしまう原因です。この切り取りひずみは、耳で聞くと「音割れ」として感じられます。楽器の音色が変わってしまったり、耳障りな雑音が混ざったりすることで、音楽の美しさや明瞭さを損なってしまいます。録音や演奏時に音が割れてしまうと、せっかくの表現が台無しになってしまうこともあります。では、どうすればこの切り取りひずみを防げるのでしょうか?まず録音する際には、入力の音量が適切であるかを確認することが大切です。録音機器には、入力レベルを表示するメーターが付いているので、このメーターが振り切れないように注意深く調整しましょう。また、演奏時には楽器の音量バランスを適切に保つことも重要です。特定の楽器の音だけが大きすぎると、全体の音量が抑えられてしまい、結果として音の迫力や表現力が失われてしまう可能性があります。ミキシングやマスタリングといった編集作業においても、切り取りひずみが発生する可能性があります。各トラックの音量バランスやエフェクトのかかり具合を調整する際には、常に音割れに注意を払い、適切な音量レベルを維持するよう心がけましょう。切り取りひずみは、少しの注意で防ぐことができます。音割れのない、クリアで美しい音を実現するために、日頃から機器の特性を理解し、適切な操作を心がけることが大切です。