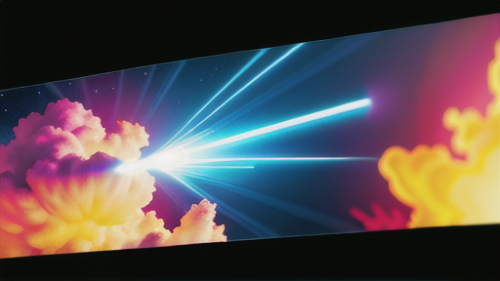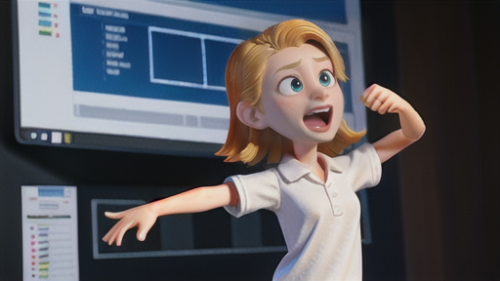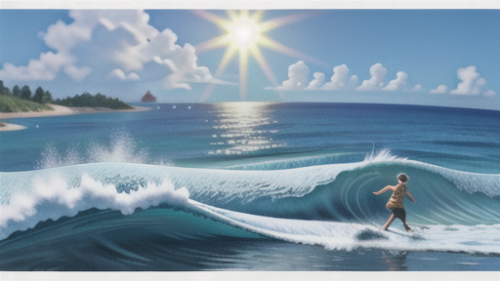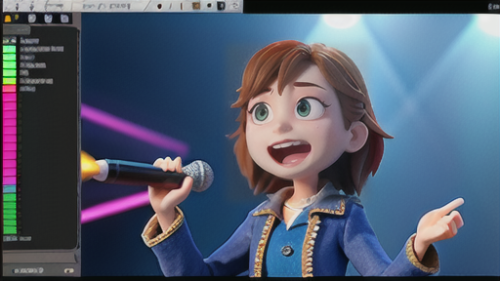音声
音声 響きの深さを知る:残響特性
音は、楽器や声が発せられた瞬間だけでなく、その音が消えた後にも、わずかな時間ですが空間に漂います。これを音の余韻、専門的には残響と言います。残響は、音響設計において空間の印象を大きく左右する重要な要素です。まるで魔法のように、音の響きだけで空間の広さや雰囲気までも変化させる力を持っています。残響は、音が壁や天井、床などの物体に反射することで生まれます。音が発生した後、直接耳に届く音だけでなく、反射した音が遅れて届くことで、音が長く響いているように感じるのです。この残響時間が長すぎると、音が重なり合ってぼやけ、何を言っているのか聞き取りにくくなってしまいます。逆に短すぎると、音に温かみがなく、乾かで冷たい印象を与えてしまいます。適切な残響時間は、空間の用途によって異なります。例えば、荘厳な雰囲気の教会やコンサートホールでは、長い残響時間によって音が豊かに響き渡り、音楽の感動をより深めてくれます。特に、クラシック音楽の演奏では、長い残響時間が壮大な響きを作り出し、聴衆を魅了します。オルガンの重厚な音色やオーケストラの華やかな音色が、長い残響によってさらに輝きを増すのです。一方、講演会や会議、あるいは劇場など、言葉を聞き取ることを目的とする空間では、短い残響時間の方が適しています。話し手の声が明瞭に届き、聞き取りやすさが重要となるからです。もし残響時間が長すぎると、声が反響して重なり、何を話しているのか理解することが難しくなります。このように、残響時間は単なる物理現象ではなく、空間の用途や雰囲気を決定づける重要な要素であり、音響設計においては、空間の音響特性を評価する上で欠かせないものなのです。