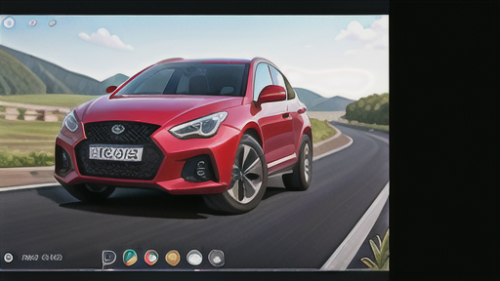規格
規格 動画を軽くする技術:帯域圧縮
動画を扱う上で、帯域圧縮は欠かせない技術です。帯域圧縮とは、動画データの大きさを縮小する技術のことを指します。動画データは、そのままでは非常に大きなサイズになりがちで、インターネットを通じて送ったり受け取ったり、コンピュータなどに保存したりする際に、多くの時間と容量が必要になります。そこで、帯域圧縮の出番です。帯域圧縮を使うことで、データの量を減らし、インターネット上でのスムーズなやり取りや、コンピュータなどへの効率的な保存を可能にします。これは、例えるなら、荷物を小さくまとめて運ぶようなものです。荷物の内容は何も変わっていませんが、小さくまとめることで、持ち運びが楽になります。同じように、帯域圧縮によって動画の情報量そのものは変わりませんが、データのサイズが小さくなることで、扱いやすさが向上します。帯域圧縮には様々な方法があり、大きく分けて可逆圧縮と非可逆圧縮の2種類があります。可逆圧縮は、圧縮前の状態に完全に復元できる方法で、主に動画の編集作業など、品質を落とさずに作業したい場合に用いられます。一方、非可逆圧縮は、多少の情報が欠落する代わりに、高い圧縮率を実現できる方法です。動画配信サービスなど、データサイズを小さく抑えたい場合によく使われます。圧縮を行うと、どうしても画質や音質が多少悪くなることもありますが、近年の技術の進歩により、画質や音質の劣化を最小限に抑えながら、高い圧縮率を実現する様々な方法が開発されています。そのため、高画質・高音質の動画を、比較的小さなデータサイズで楽しむことができるようになりました。このように、帯域圧縮は、動画を扱う上でなくてはならない重要な技術となっています。