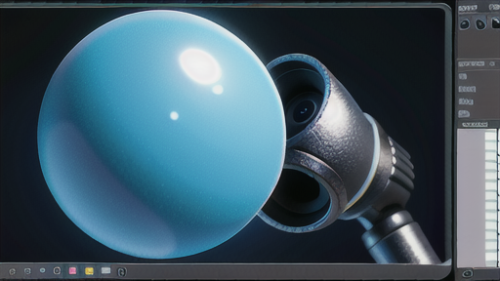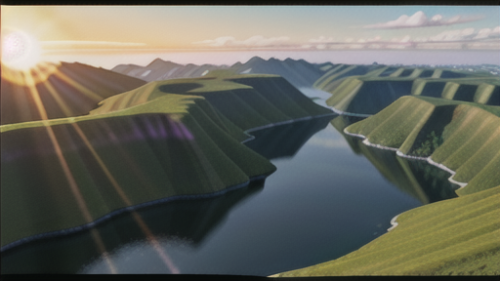画質
画質 クロスカラー:虹色のちらつき対策
画面に現れる色のちらつき、気にしたことありますか?時折、テレビを見ていると、虹色の変な光が見えることがあります。特に、細かい縞模様の服を着ている人を見ると、その縞模様に沿って虹色の光が走っているように見えることがあります。これは「色のまじり」と呼ばれる現象で、一体どうして起こるのでしょうか?テレビ放送では、送られてくる映像信号の中に、明るさを表す信号と色を表す信号が一緒に入っています。この2つの信号をうまく分けて、正しく表示することで、私たちはテレビで色鮮やかな映像を見ることができるわけです。ところが、この2つの信号を分ける作業がうまくいかない場合があります。例えば、明るさの信号の中に色の信号が少し混ざってしまう、そんなことが起きるのです。色の信号が明るさの信号に混ざってしまうと、本来は明るさだけを表すはずの信号に色が付いてしまいます。これが色のまじりの原因です。まるで絵の具を混ぜるように、明るさの信号に色が混ざってしまい、虹色のちらつきとして見えてしまうのです。特に、細かい縞模様のように明るさが急に変わる部分で、この現象はよく起こります。白黒の細かい縞模様を想像してみてください。白と黒が交互に並んでいるので、明るさが急に変化していますよね。この明るさの急な変化が、色の信号と間違われてしまうのです。その結果、白黒の縞模様のはずなのに、虹色の光が走っているように見えてしまうのです。例えば、白黒の細かい縞模様の服を着た人がテレビに映ると、縞模様の部分に虹色のちらつきが現れやすいです。これは、白黒の縞模様の明暗の差が、色の信号だとテレビが勘違いしてしまうからです。本当は存在しない色が、画面上に現れてしまうのです。このように、色のまじりは、信号をうまく処理できなかったために起こる現象と言えます。