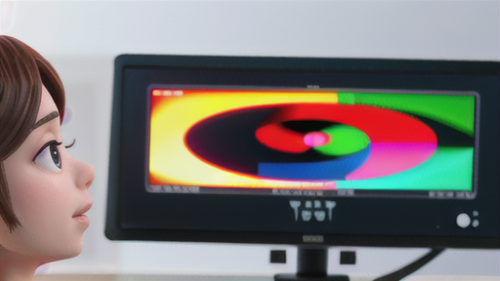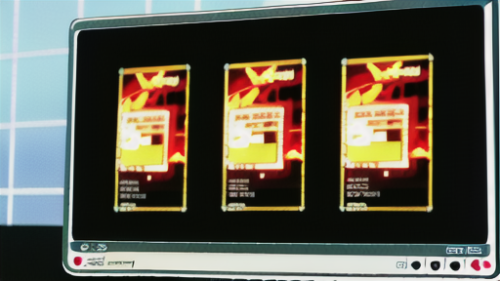撮影機器
撮影機器 動画撮影の必需品、照明機材PULSARをご紹介
動画を撮影する際に、光はとても重要です。被写体を明るく照らし出すことはもちろん、陰影を付けることで奥行きや立体感を出すこともできます。そのため、照明機材は動画制作に欠かせません。数ある照明機材の中でも、イタリアの会社が作っている『パルサー』は、現場で頼りになる照明機材の一つです。このパルサーには、五百ワットの熱を帯びた光を出す電球が使われています。この電球は、強い光で被写体を照らすことができます。人物を撮影する時だけでなく、商品や建物、景色など、どんな場面でも活躍してくれるでしょう。パルサーの一番の特徴は、持ち運びしやすいことです。照明器具とそれを立てる台が三つずつ、そして、それらをしまう箱がセットになっています。そのため、撮影場所に簡単に持っていくことができます。撮影所だけでなく、他の場所で撮影することが多い現場では、特に役に立つでしょう。また、この電球が出す温かみのある光は、被写体に自然な影を作り、立体的に見せる効果もあります。まるで太陽の光を浴びているかのような、自然で美しい映像を撮ることができます。パルサーは、動画を作るプロにとって、心強い味方となるでしょう。