動画編集の基礎:被写体が切れるのを防ぐ

動画を作りたい
先生、「きれる」って動画制作の用語でどういう意味ですか?

動画制作専門家
いい質問だね。「きれる」は、画面に映っているものが画面の外にはみ出て見えなくなることだよ。たとえば、人が歩いて画面から出てしまう場合などだね。

動画を作りたい
なるほど。画面から出て見えなくなることですね。では、画面の中に半分だけ映っている場合は「きれている」というのでしょうか?

動画制作専門家
半分だけ映っている場合は「切れている」とは言わないよ。完全に画面の外に出て見えなくなった場合に「切れている」と言うんだ。半分映っている場合は「フレームアウトしかけている」と表現する方が適切だね。
きれるとは。
動画を作る際の言葉で「切れる」というものがあります。これは、写しているものが画面から外に出てしまうことを指します。
画面の枠を意識する

動画を撮る際には、写したいものが画面からはみ出してしまうことがよくあります。画面からはみ出すことを、業界用語で「切れる」と言います。これは、見ている人に違和感を与え、せっかくの動画の質を下げてしまう原因の一つです。動画作りで一番大切なのは、画面の枠をきちんと意識することです。
撮影を始める前に、まず写したいものが画面の中にきちんと収まっているかを確認しましょう。もし、人や動物など動くものを撮る場合は、動いても画面から出ないように注意が必要です。被写体がどう動くのかを予想し、カメラの位置を変えたり、ズームの倍率を調整したりすることで、「切れる」ことを防ぐことができます。
また、写したいものが画面の端に寄りすぎていると、窮屈な印象を与えてしまいます。画面の端と写したいものの間には、適切な余白を作ることが大切です。ちょうど良い余白を作ることで、見ている人は心地よく動画を見ることができます。
画面の枠と写したいものの関係性を常に意識することで、より見やすく、見ている人が快適に感じられる動画を作ることができます。少しだけ画面に余裕を持たせるように構図を作ることで、写したいものの魅力を最大限に引き出すことができるでしょう。
| 問題点 | 対策 | 目的 |
|---|---|---|
| 被写体が画面からはみ出す(切れる) |
|
違和感を与えず、動画の質を向上させる |
| 被写体が画面端に寄りすぎている | 画面の端と被写体の間に適切な余白を作る | 窮屈な印象を与えず、心地よく見れるようにする |
| 画面の枠を意識していない | 画面に少し余裕を持たせる構図にする | 被写体の魅力を最大限に引き出す |
被写体の動きを読む

動画を撮る上で、写したいものが画面から切れてしまうのは避けたいものです。特に動いているものを撮る時は、次の動きを予想して撮ることが大切です。例えば、人が歩いているところや車が走っているところを撮る時、どちらの方向へどれくらいの速さで動いているのかを考えながらカメラを動かす必要があります。写したいものが右へ動いているなら、画面の左側に十分な空きを作っておくことで、画面から切れてしまうのを防ぐことができます。
動きを予想する練習を何度も重ねることで、滑らかで自然な動画を撮ることができるようになります。また、カメラの拡大機能を使うのも良い方法です。写したいものが画面から切れそうになったら、画面を広くして全体を捉え直すことで、切れてしまうのを防ぐことができます。
被写体の動きを読み取ることは構図を考える上でも重要です。被写体がこれからどのように動くのかを予測し、その動きに合わせて画面の構成を考えることで、より効果的な映像表現が可能になります。例えば、被写体が画面奥に向かって走っていく場合、画面手前に十分な空間を設けることで、被写体の動きを強調することができます。また、被写体の視線の先に空間を設けることで、被写体の感情や意図を表現することができます。
動きを常に意識し、カメラを適切に操作することが、質の高い動画を作るためには欠かせません。被写体の移動方向や速度だけでなく、動きのリズムや変化にも注意を払うことで、より生き生きとした映像を捉えることができます。急な方向転換や速度変化を予測し、それに合わせたカメラワークを行うことで、見ている人が動きについていけるようにし、より快適な視聴体験を提供することができます。
焦点を合わせる機能の使い方も大切です。動いているものに焦点を合わせ続けることで、見ている人がどこに注目すれば良いのかが分かりやすくなります。また、背景をぼかすことで、動いているものがより際立ち、印象的な映像を作り出すことができます。
これらの技術を組み合わせることで、動きのある場面を効果的に捉え、見ている人を惹きつける動画を作ることができます。
| 目的 | 具体的な方法 | 効果 |
|---|---|---|
| 被写体を画面内に収める |
|
|
| 効果的な映像表現 |
|
|
| 生き生きとした映像 |
|
|
| 見ている人の視線誘導 |
|
|
適切な撮影機器を選ぶ
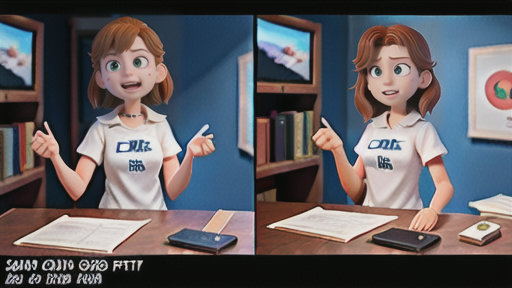
動画を撮る道具選びは、物が画面から切れてしまう「切れ」に大きく関わってきます。例えば、広角レンズは広い範囲を写せますが、被写体が小さく映り、画面から切れやすくなります。遠くの物を大きく写せる望遠レンズは、写せる範囲が狭いため、動く被写体を追うのが難しく、これもまた「切れ」の原因になります。つまり、撮るものや状況に合わせてレンズを選ぶことが大切です。
カメラの揺れは「切れ」に繋がるので、三脚やスタビライザーなどの補助道具を使うと安定した映像を撮ることができます。三脚はカメラを固定する道具で、風景や動きの少ない物を撮る時に役立ちます。スタビライザーは、動きながらの撮影でも滑らかで安定した映像を撮れるように手ブレを軽減してくれる道具です。動き回る被写体や、歩きながらの撮影で力を発揮します。これらの道具を使うことで、被写体が画面から切れるのを防ぎ、より良い映像を作ることができます。
さらに、動画を記録する本体にも気を配る必要があります。最近の機器は高画質で動画を記録できますが、その分データの量も大きくなります。記録するための記憶装置の容量を確認し、足りなくならないように注意が必要です。また、撮影中に電池が切れてしまうと、せっかくの撮影が中断されてしまいます。予備の電池を用意しておく、または機器を電源に繋ぎながら撮影するなどの工夫が必要です。撮影機器の機能をよく理解し、適切に使うことで、高品質な動画を作ることができます。
照明器具も動画の質に大きく影響します。自然光で撮影する場合、天候や時間帯によって明るさが変化するため、被写体が暗く映ったり、白飛びしたりすることがあります。照明器具を使うことで、明るさを調整し、被写体を綺麗に映し出すことができます。また、被写体の背景を明るくすることで、被写体を際立たせる効果もあります。
撮影機器にはそれぞれ特徴があるので、それらを理解し、状況に合わせて使い分けることが、より良い動画制作には欠かせません。
| 種類 | 効果 | 注意点 | 使用例 |
|---|---|---|---|
| 広角レンズ | 広い範囲を写せる | 被写体が小さく映り、画面から切れやすい | 風景撮影 |
| 望遠レンズ | 遠くの物を大きく写せる | 写せる範囲が狭く、動く被写体を追うのが難しい | スポーツ撮影、野生動物撮影 |
| 三脚 | カメラを固定し、安定した映像を撮れる | 固定されているので、動きのある被写体には不向き | 風景撮影、インタビュー |
| スタビライザー | 動きながらの撮影でも滑らかで安定した映像を撮れる | – | 動き回る被写体、歩きながらの撮影 |
| 記録装置 | 動画を高画質で記録できる | 容量が大きいため、容量不足に注意が必要 | – |
| バッテリー | 撮影機器の電源 | 撮影中に電池切れにならないように注意が必要 | – |
| 照明器具 | 明るさを調整し、被写体を綺麗に映し出せる。被写体を際立たせる効果もある。 | – | 人物撮影、商品撮影 |
編集ソフトを活用する

動画編集ソフトは、撮影後の映像をより良く見せるための強力な道具です。撮影時にどうしても起きてしまう「画面から被写体が切れてしまう」現象も、編集ソフトを使えばある程度修正できます。
最近の動画編集ソフトには、被写体を自動で追いかける機能が備わっているものがあります。この機能を使えば、被写体が動いても、常に画面の中央に捉え続けることができ、「切れる」現象を防ぐことができます。たとえ被写体が画面から切れてしまっても、トリミング(切り抜き)機能を使えば修正可能です。画面の不要な部分を切り取ることで、被写体が画面の中心に来るように調整できます。また、被写体が急に動いて画面から切れてしまった場合などは、動画の再生速度を変えることで、動きを滑らかに見せることができます。再生速度を遅くすることで、急な動きが緩やかになり、「切れる」現象が目立ちにくくなります。
動画編集ソフトでできる修正には限界があります。編集作業に多くの時間を費やすよりも、撮影段階で「切れる」現象をなるべく少なくすることが大切です。撮影時に被写体の動きを予測し、適切なカメラワークを心がけることで、編集作業の負担を減らすことができます。被写体が動かないように固定したり、カメラを固定して撮影するのも一つの方法です。
質の高い動画を作るためには、撮影と編集の両方が重要です。撮影時に「切れる」現象を最小限に抑え、編集ソフトを効果的に活用することで、より見やすく、魅力的な動画に仕上げることができます。
| 動画編集ソフトの機能 | 効果 |
|---|---|
| 自動追尾機能 | 被写体を常に画面中央に捉え、「切れる」現象を防ぐ |
| トリミング(切り抜き)機能 | 画面の不要な部分を切り取り、被写体を画面の中心に調整 |
| 再生速度変更機能 | 急な動きを滑らかにし、「切れる」現象を目立ちにくくする |
動画制作のポイント
- 撮影段階で「切れる」現象をなるべく少なくする
- 被写体の動きを予測し、適切なカメラワークを心がける
- 被写体を固定したり、カメラを固定して撮影する
- 撮影と編集の両方が重要
練習と経験を積む

動画を滑らかに繋げる技術は、一朝一夕で身につくものではありません。まるで熟練の職人技のように、練習と経験の積み重ねが何よりも大切です。
まずは、身近にあるものから被写体にして、動画撮影に挑戦してみましょう。花や動物、街の風景など、何でも構いません。大切なのは、様々な被写体や状況で撮影を繰り返すことです。晴れた日、曇りの日、屋内、屋外など、色々な環境で撮影することで、光の状態や背景とのバランスを掴むことができます。
撮影中に被写体が急に動いてしまったり、カメラワークが乱れて動画が繋がらなくなる、いわゆる「きれる」現象に遭遇することもあるでしょう。失敗は成功のもとです。なぜ「きれる」現象が起きたのか、どうすれば防げたのかを振り返り、次に活かすことが大切です。
上手な動画制作者の作品を見ることも、学ぶ上で非常に効果的です。どのように被写体を捉えているのか、カメラはどのように動いているのか、構成や編集はどうなっているのかなど、注意深く観察することで多くのヒントを得られるでしょう。動画共有サイトや動画投稿サイトで公開されているメイキング動画なども参考になります。また、図書館や書店で撮影技術に関する本を探したり、インターネットで情報を集めるのも良いでしょう。
技術的な知識を学ぶだけでなく、被写体の魅力を最大限に引き出すための構図や演出についても学ぶことが重要です。被写体の表情や動き、背景とのバランス、光の使い方などを工夫することで、より印象的で心に残る動画を制作できるようになります。
動画制作は、継続的な学習と実践が不可欠です。焦らず、一つずつ技術を習得し、経験を積むことで、必ず視聴者に感動を与える動画を作り上げることができるでしょう。
| 動画制作のポイント | 詳細 |
|---|---|
| 練習と経験の積み重ね | 様々な被写体や状況で撮影を繰り返すことが重要。色々な環境での撮影を通して、光の状態や背景とのバランスを掴む。 |
| 失敗から学ぶ | 動画が「きれる」現象などが起きた場合は、原因を分析し、次に活かす。 |
| 他者の作品から学ぶ | 上手な動画制作者の作品を観察し、構図やカメラワーク、編集などを学ぶ。メイキング動画なども参考になる。 |
| 技術的な知識を学ぶ | 撮影技術に関する書籍やインターネットの情報などを活用する。 |
| 構図や演出を学ぶ | 被写体の魅力を引き出すための構図や演出、光の使い方などを学ぶ。 |
| 継続的な学習と実践 | 焦らず、一つずつ技術を習得し、経験を積むことで、感動を与える動画を作り上げることができる。 |
